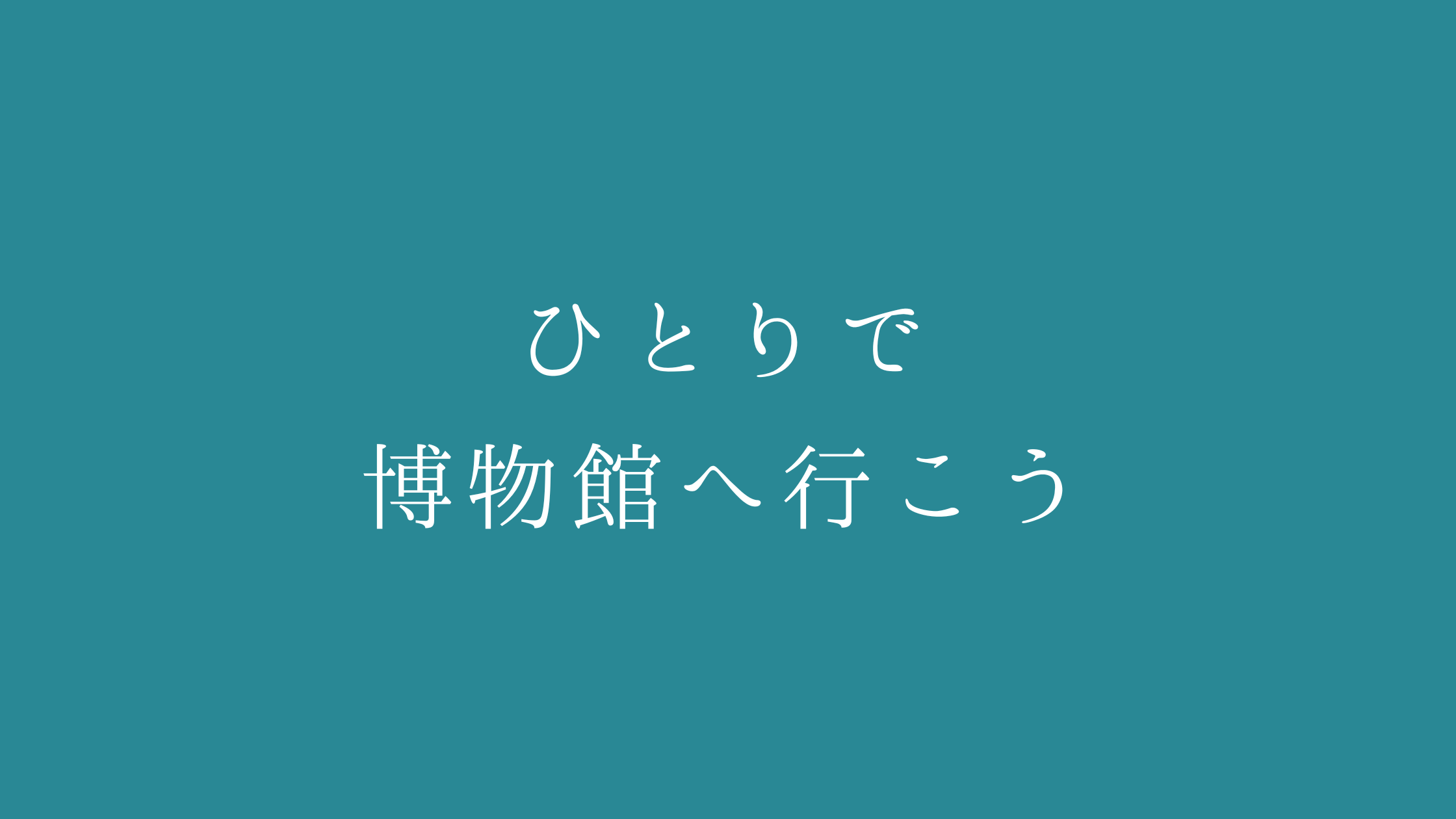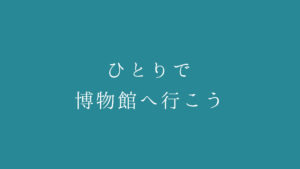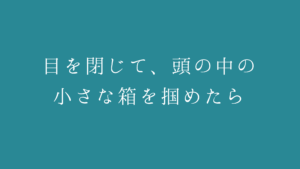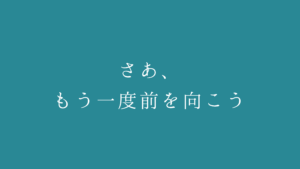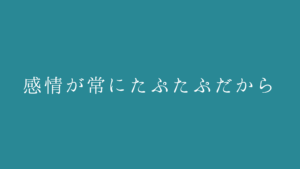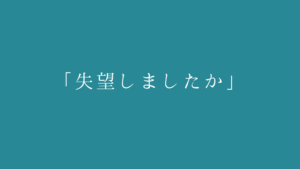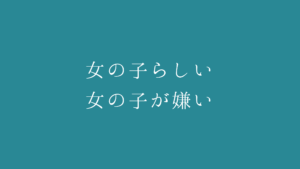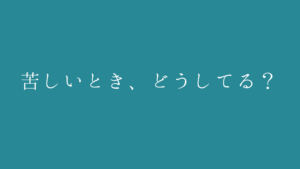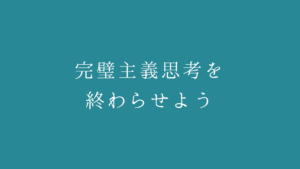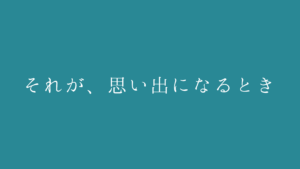「博物館に行くのが好き」と言うと、なんとなく変な空気になるのはなんでなんでしょうか。
私が博物館に行くのが好きになった理由は、高校の日本史の授業の影響からです。特に稲作文化が伝わり農耕社会が形成されたとされる「弥生時代」が好きで、稲を刈り取る際に使われていた石包丁や、豊作を祈るお祭りのために使われていた銅製の金属器などを見ると、「これ資料集でみたやつだ!」と感情が昂るのを感じます。
小さな道具ひとつにしても、じっくりと解説を読んでみると、当時を生きていた人の苦悩や遊び心がありありと目の前に浮かんできます。今日見たものの中で印象に残ったのものは、今でいう漏斗の元になったという道具。当時は、お米を別の容器に移し替えるための道具として使われていたもので、解説書には「詰まりを防ぐために緻密に網目を調整することが必要だった」と書かれていました。詰まりが起こるたびに、悪態をつきながらちまちま網目の大きさを調整していたのかなあ。そんな昔の人の様子が思い浮かんできて、ちょっと笑えました。そして、昔の知恵が現在でもきちんと機能しているという事実に関心するのです。
こうして昔と今の繋がりを意識すると、自然と背筋が伸びるような気がします。
展示物を眺める私に向かう想いや視線を感じることがあるからです。
それらを感じると、自然と「昔の人の想いや経験を無駄にしないように私がきちんと生き抜かなきゃ」という感情が湧いてきます。オカルトチックな話にはしたくないのであまり深くまで突っ込まないでほしいのですが、そういう類のものを受け取る瞬間が確かにあります。
これは一種の脅迫観念のようなものですが、私にとってはそれがとても心地よく作用するのです。
先の時代にしっかりと受け継がれた想い。技術革新や外部からの影響によって形が変わった文化。記録ごとすっかり消えてしまった歴史。
もしかしたら、今の私たちが残す歴史や文化だって、これから先に生きる人たちからしてみれば、それほど大したものではないのかもしれません。それでも私は、今を一生懸命生きることで、こうして後世に何かが伝わる可能性があるのなら、私は今抱えている悩みや思いにきちんと対峙した上で、「歴史や文化」として形に残したいなと思っています。そういう意味では、このブログを書いている意義も、そこに着地します。
ちなみに、私は過去世で弥生時代に生きていた人物なんだろうなと思います。当時の石器などになんとなく懐かしさを感じることと、お米が異常なくらい好きだからです。具のないおにぎりが大好物(塩もなし)で、定食なんかは先におかずや汁物、漬物まで食べあげてからお米に手をつけます。割と小食な方ですが、お米なら一食で3合はいけます。パンも好きですが、やはり米粉パンが一番好きですね。